COI-NEXT シンポジウム2025を開催しました
11月7日(木)にアオーレ長岡にて『JST 共創の場形成支援プログラム(COI-NEXT)「“コメどころ”新潟地域共創による資源完全循環型バイオコミュニティ拠点」シンポジウム2025』を開催しました。
本シンポジウムでは本拠点の活動報告や研究報告に加え、今後の本拠点の活動の展望について議論や交流、情報交換を行いました。当日は県内外から会場・オンラインで多くの方にご参加いただきました。ご参加いただきました皆様ありがとうございました。
第一部では、鎌土重晴学長(長岡技術科学大学)、平野博紀様(文部科学省)、西村訓弘様(国立研究開発法人科学技術振興機構:副プログラムオフィサー)による開会の挨拶と、本拠点への期待についてお話しいただきました。

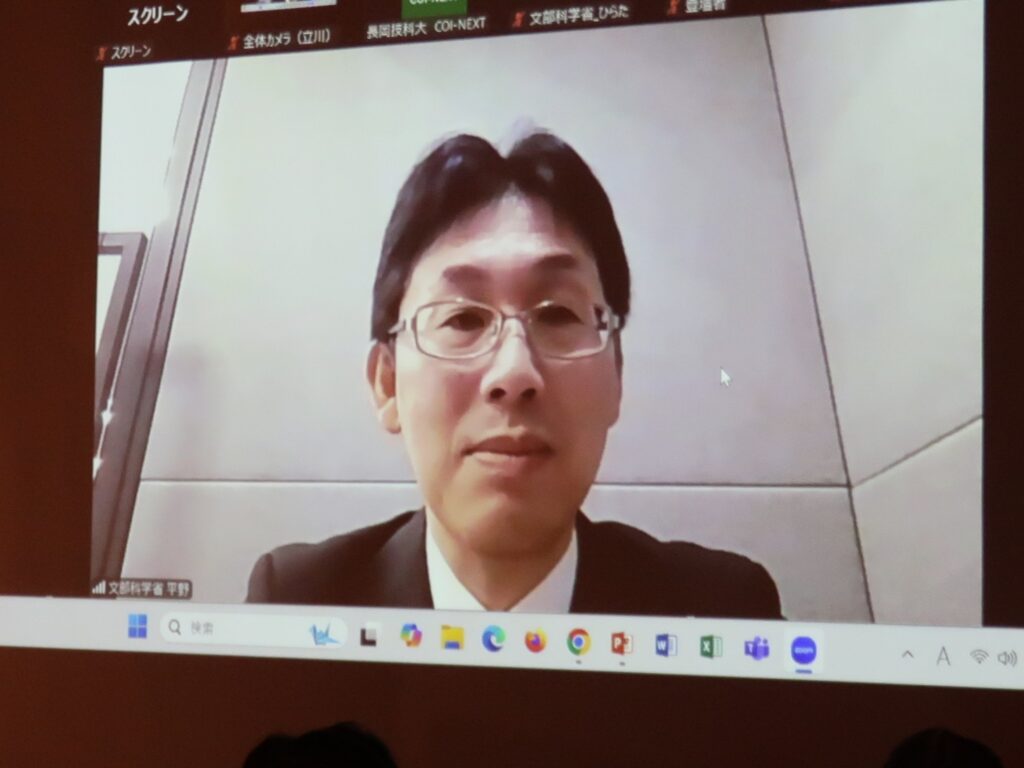
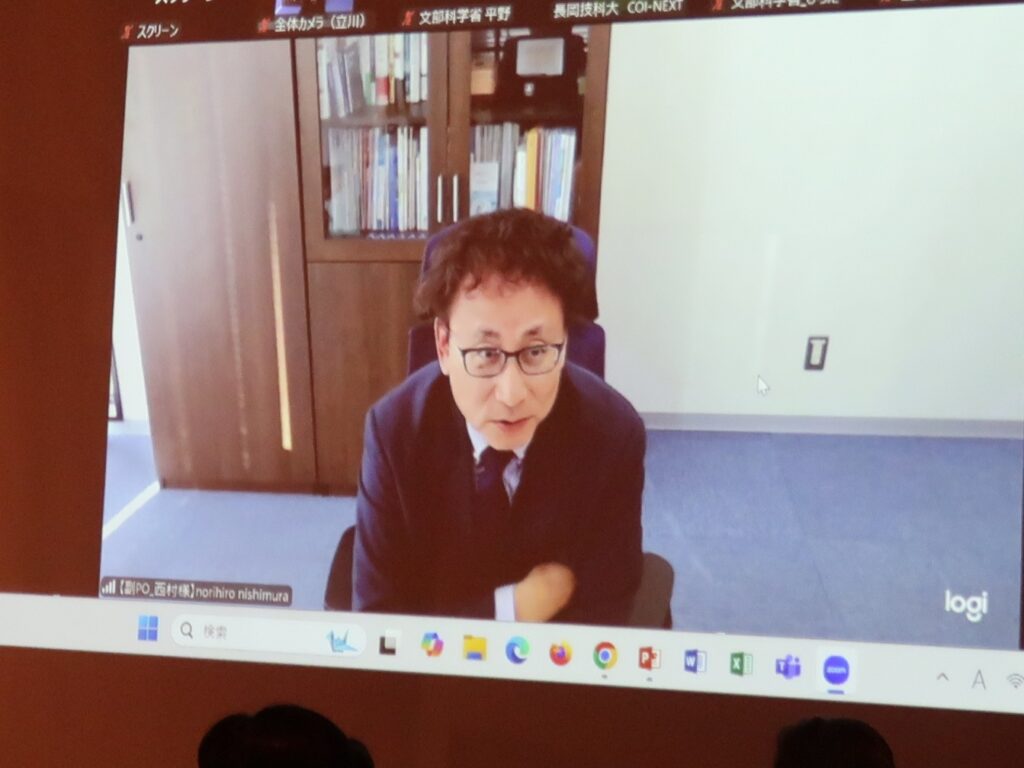
その後の「拠点活動報告」において、本拠点プロジェクトリーダーの小笠原渉 教授より、本事業のめざすものと、各研究開発課題の概要と成果についての説明、稲作を成長路線に回帰させるための今後の活動、2025年5月に完成したリージョナルGXイノベーション共創センターの設備と役割について説明がありました。今回、本COI-NEXT拠点の取組みに初めて触れる参加者が多かったことから、事業の背景について詳しくご説明を頂きました。多くの一人ひとりが自分ごととして循環型社会を作る一員になろうとすることが大切であるとのメッセージで結びました。
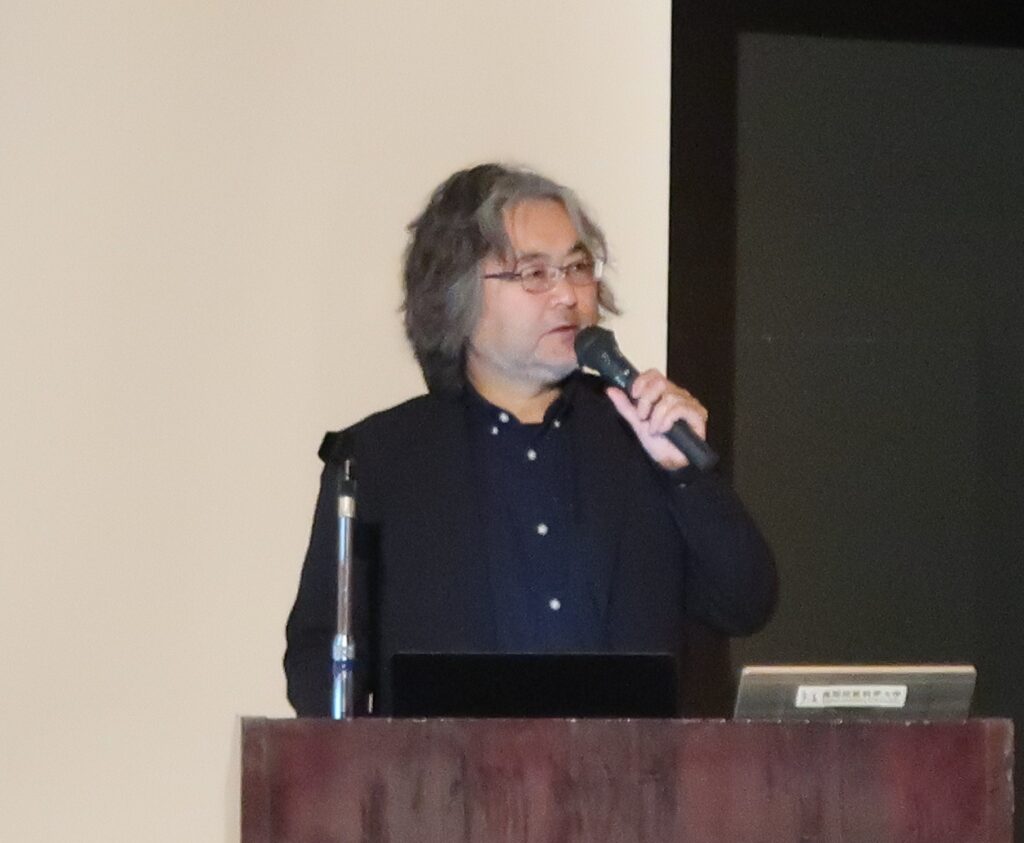


「研究活動報告」では、まず本学の中村彰宏助教から、研究概要について説明がありました。研究開発課題4における未利用資源を活用した酵母による油脂の生産技術について、その意義から現在までの技術的進捗、今後の展望までをお話頂きました。続いて本学の渡利高大准教授から、微生物の力を活用した水浄化システムの開発や、陸上養殖に向けた技術開発と展望についてお話しいただきました。
今回のシンポジウムでは、「ミライへつなぐ」をテーマとして、”コメどころ”新潟の豊かな食と文化をミライへつなぐために、若い世代がどのような思いで事業を継承し、新たな価値を生み出そうとしているのかを聞き、共に考える機会とすることを企画し、開催いたしました。
第二部の「講演」では、菊水酒造市場開発本部海外営業担当の髙澤俊介様と、ホーネンアグリ株式会社代表取締役小林ひかり様にご講演いただきました。髙澤様からは、「ミライにつなぐ酒蔵」と題して菊水酒造のこれまでの歴史から、日本酒産業の危機、酒粕を資源として活用した事例、地域の人々との共創に向けた取組みや発信拠点KIKUSUI蔵GARDENの整備などについてお話しいただきました。酒造メーカーでありながら、子供から大人まで全世代の人々を巻き込んだミライの人づくりを目指されていると話されていました。


小林様からは、「ミライへつなぐ土づくり」のテーマで、ホーネンアグリ社の歩んできた歴史、培ってきた技術、農業を取り巻く環境変化とそれらを乗り越えるための3つの挑戦として、資源循環の土づくり、地域連携の意義、バイオ技術の積極的な導入についてお話しいただきました。ご講演の最後には、土づくりとともに人づくりが大切であり、人が育ち、活躍できる環境づくりに取り組まれていることをお話しされていました。
第三部の「パネルディスカッション」では、パネラーとして、菊水酒造の髙澤様、ホーネンアグリの小林様、本拠点の渡利准教授、中村助教から、モデレーターとして、本拠点副プロジェクトリーダーの中村徹特任教授からご登壇いただきました。企業と大学それぞれにおける人づくりのお話から、思い描くミライとそこへ向けての技術開発のこれから、産学連携の意義について、それぞれの立場から興味深い意見交換が行われました。さらに、企業のお二人には継承すると決めたきっかけを、本拠点のお二人にはアカデミアに進むきっかけをお話しいただきました。COIーNEXT本拠点のビジョンを残り6年半で達成するためには、本事業がめざすミライを地域の方々と共有することや、若い人々の熱意を結集させることが不可欠です。本シンポジウムを通じて新しい人と人とのつながりが生まれ、若い世代がどのような考えで未来をつくることを決意したのか、多くの学びや発見を得る有意義な機会となりました。


閉会には長谷川亨様(長岡市:産業政策監)よりご登壇いただき、会の総括となるご挨拶を頂戴しました。

今後もステークホルダーの皆様と共に、地域資源完全循環型バイオコミュニティ拠点の実現に向けて邁進してまいります。


